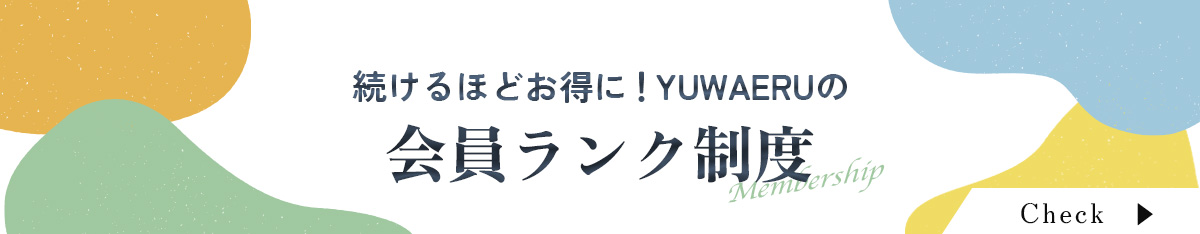【Patina哲学】第四回 日本の国旗

モノ・コト・ヒトの経年変化を味わい楽しむブログ
2018年2月11日は建国記念日。そういう日には、必ず家のドアに小さく、日本の国旗が掲揚されているのを見かけるが、それを見るのが好きだ。その日を迎えた日本に、おめでとうと祝福をしているようだから。
日本の国旗はシンプルで、美しい。
日本の国旗に抱く複雑な気持ち
小学生の頃、地元でアジア大会が開催されたとき、アジア各国の国旗をみんなで作りましょうという課題があった。わたしは光栄にも、日本の国旗の担当になった。そのとき中国に興味があり、日本の国旗の美しさを知らなかったわたしは、不謹慎にも、白に丸かいて赤塗って終わりじゃん、と思ってしまった。事実、ほかの国の国旗と比べたら、それをつくるのに時間はかからなかった。簡単すぎて不満だった。
小学生か中学生だったか、記憶が定かでは無いが、式典で国旗を掲揚するとき、起立する。そのとき、立たない先生がいた。腕を組んで不満そうに座っていた。あとで知ったが、広島県の一部の学校教育の現場では、国旗掲揚や国歌斉唱に異をとなえる人々が一定数いる。
1999年広島県世羅高校の校長先生が、この問題で悩み、自殺した。この事件を知ったとき、あの不満そうに腕を組んでいた先生の顔を思い出した。
異をとなえる人々が主張していることを、ざっくり表現すれば、戦争につながる記憶を、国旗や国歌が内包しているからだ。それに敬礼できないと、拒絶する。広島は原爆の被害にあった都市であり、平和教育に熱心であるがゆえに、戦争につながるイメージを拒絶するのだろう。
子どもの頃、そういうところで育ったせいか、国旗や国歌に対して、複雑な感情を抱くようになった。
モノの変化ではなく、モノに背負わせたイメージが変わるとき
それが変化したのは、日本を一度離れて、上海で暮らしたとき。中国の国旗は赤い。町中至る所に赤字にスローガンの書かれた旗が飾ってあった。赤は革命の色で共産党のシンボルカラー。上海で暮らしているとき、いつも何かと闘っていた。孤独、言語、中国人、埃、陰鬱な空、日本人、どこかでわたしを狙っている泥棒という架空の存在、そして自分自身と。そのモチベーションには赤がよく似合う。
日本から離れて時間が経てば経つほど、日本で暮らしていたときは当たり前すぎて気づかなかった小さなことが、懐かしく、大切なものに感じられるようになった。
例えば、全然交通量がないのに、しっかり引かれて誰も通らない横断歩道とか、自転車の車輪がカラカラ回る音とか、低い山と点在する瓦の屋根の家とか、青い空と白い雲と緑の山のコントラストとか、夕方のカラスの声とか、匂いのしない空気とか、透明な空間とか。
日本に暮らしていればどうでも良すぎて記憶にも残らなかったり、意識する次元のことであると認識すらしなかったことは、一度それを失うと、なぜかふとした瞬間に、無意識に自分の記憶を遡ってくる。
そういう小さなイメージが、国旗の白地の余白にたくさん詰め込まれていった。日本を体現するもの。言葉にできないけど、余白にあるもの。
いつしか、よく知らなかったからこそ、嫌な感じのするものというイメージを与えていた、わたしの中の日本の国旗が、クリーンで、どこかに飛んでいってしまうわたしの意識を戻してくれる、基地のような存在に変わっていった。
わかりやすい言葉で表現すれば、ふるさとみたいなもの。田舎から上京すれば、田舎がふるさとの定義だろう。しかし、田舎からいきなり海外へ行ったわたしは、日本そのものがふるさとになった。どこか特定の場所ではなく、それが内包する、言葉にできないすべての感覚が集約する場所。
イメージが時間の中に置き去りにされたら、風評被害になる
国旗がイメージするものは、長い時間の中に蓄積された多様な価値を含む。その中には、戦争の記憶もあるだろう。だが、戦争のイメージだけが国旗を体現するなら、それは時間の経過も、空間の奥行きも、全部無視している。
戦争の記憶だけがあったのではない。戦争の記憶も、その中にはあったのだ。しかしイメージが強烈すぎて、いつしか記憶や体験がそのもの自体を凌駕したのかもしれない。
強烈なイメージは、どこかの時間にとどまったままだ。むしろ、イメージがそこで時間の流れを止める。風評被害が発生するのも、時間がとまったとき。それは、経年変化の考えと真逆のベクトルだ。物事は常に変化し、時間が止まることはないのに、敢えて止めている。その思考回路では、いつまで待っても、いくら味わいのあるものに接しても、その真価はわからないだろう。
経年変化は、そのものが保有する時間と空間を、垣根のない自分が共有して初めて、味わいになる。イメージのない裸の目で、モノに接したときに初めて、経年変化を捉えることができる。そのとき、経年変化がPatina(パティーナ)、すなわち味わいに感じられるようになる。
身近なものにこそ、昔から当たり前にあるものにこそ、それは密かにくっついている。見えるかどうかは自分次第なのだと思う。

Patina哲学第四回 版画タイトル:切通坂