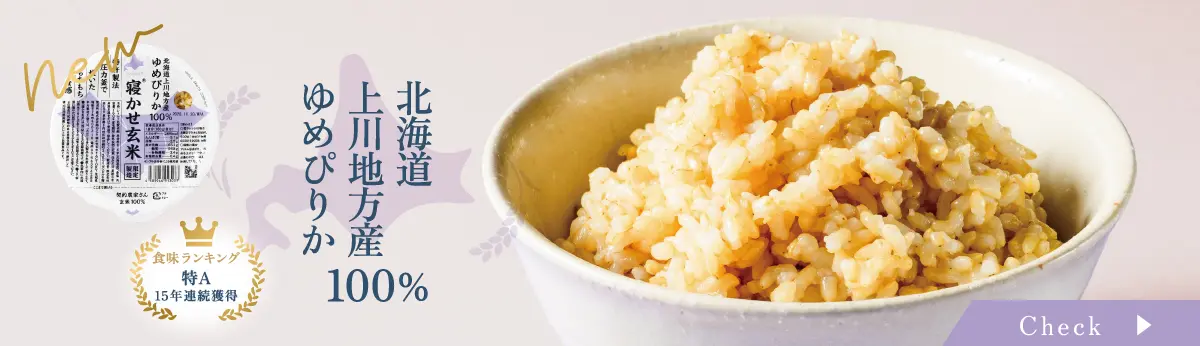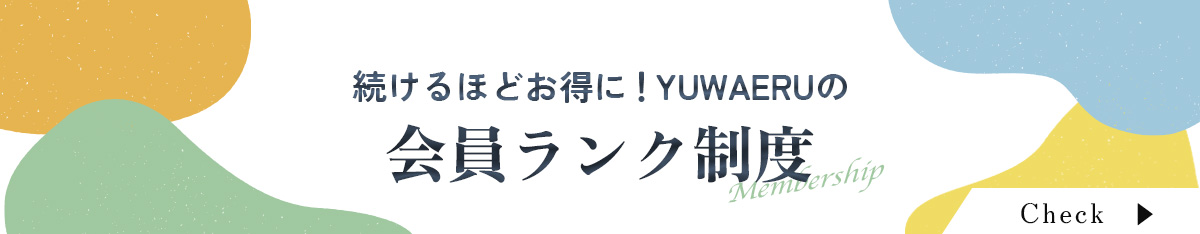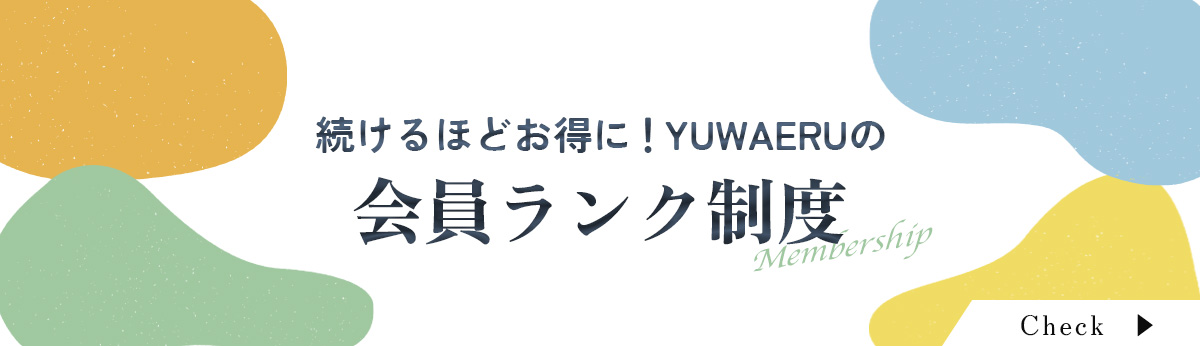群言堂日記-12石見銀山街歩き
インターンの休日に、石見銀山の町歩きツアーに参加しました。
ツアー内容は午前と午後に分かれていて、午前は国道31号線付近の城上神社を始点に、800mの江戸情緒あふれる町並み地区を歩くツアー。
そして午後は2.3kmを歩き「龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)」という銀の採掘が行われていた洞窟を目指す銀山地区を歩くツアーです。
まずは町並み地区を歩くツアーに参加。参加費は500円。ガイドさんの説明を受けながら歩きます。

城上神社。おさんぽ中の園児たちといっしょに参拝しました。
城上神社は群言堂・阿部家のある大森町と銀山の氏神様が祀られている神社で、天井に描かれた「鳴き龍」という極彩色の龍の絵が有名です。
「鳴き龍」という名前の由来は、天井絵の真下で拍手をすると音が共鳴するためなんだとか。

柏手を打つとビーーーンと音が響きます。
石見銀山は江戸時代、幕府の天領だったため代官所も建てられましたが、武士が住む武家屋敷と商人が住む町家が入り混じって建てられていることが大変珍しい町並みとされています。

大森代官所跡。
代官所の建物は明治以降も軍役所や裁縫学校として使われていたそう。

町並み最大の商家、熊谷家。

町並み。入り口が直接道に面しているのが町人の家の特徴。
景観を守る工夫が凝らされながら、今でも各家には人が暮らしています。

阿部家のように庭を設けてあるのが武家屋敷。どんなに裕福な町人でも、武士と同じように庭先のある家に住むことは許されなかったのだそう。
いまでこそ、古き良き町並みを求めて人が集まるようになった石見銀山ですが、銀の採掘量が減り、衰退した後は、高度経済成長の波に置き去りにされ過疎化が進みました。しかし、それが幸いし、いまこうして当時の町並みが手付かずで残されたのだと言います。

「親子格子」という長短交互に組まれた格子はこの地域ならではなんだとか。
今では電柱が地中化され、消火栓、各家のメーター、自動販売機も木のカバーが設けられています。景観を守る工夫が随所に施されています。




群言堂石見銀山本店も。古い町並みの良さを活かしながらもどこか個性的。中にはカフェ、雑貨や衣料品売り場があります。

美しい町並みは30分ほどで歩くことができ、信号もコンビニもない、本当にのどかな町・・・銀山跡地とこの町の景観の価値を認められ、世界遺産登録された石見銀山には、いまは多くの人が訪れていますが、この土地には、かつて廃れたからこそ残された価値もあります。
そんな町やモノの価値に気づく人が増えたことで、この町に多くの人が集まるようになったのだと。そして、私たちが捨ててしまった、失ってしまったものはなにか、その価値はなにかと、考えさせられます。